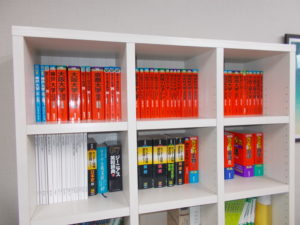梅花女子大学看護保健学部、合格❢(2020年11月07日 更新)

誠心館とSEED-TIMES合わせて高3の受験生は合計16名。
今のところ、梅花女子大、大阪電気通信大(2名)合格。
そのあとの公募組は
大阪経済大学、四天王寺大学、大和大学、甲南女子大学、森ノ宮医療大学、奈良大学、武庫川女子大学、大阪工業大学、関西医科大学、兵庫医療大学等々。。。。
さらに本命の関西学院大学、関西大学、大阪教育大学、兵庫県立大学
毎年のことですが、合格と不合格は常に紙一重。
最後まであきらめずに自分を信じて勉強してほしい。
そして、高2生は高3生のガンバリを横目に、今から入試に向けて貪欲に勉強すればワンランクもツーランクも上の大学に合格できること間違いなしです^^
今からSEED-TIMESに来ている高2生は担当講師がみっちりレールを敷くので、塾を信じてついてきてください^^
生徒と保護者様の期待に応える自信があります❢
ともに。