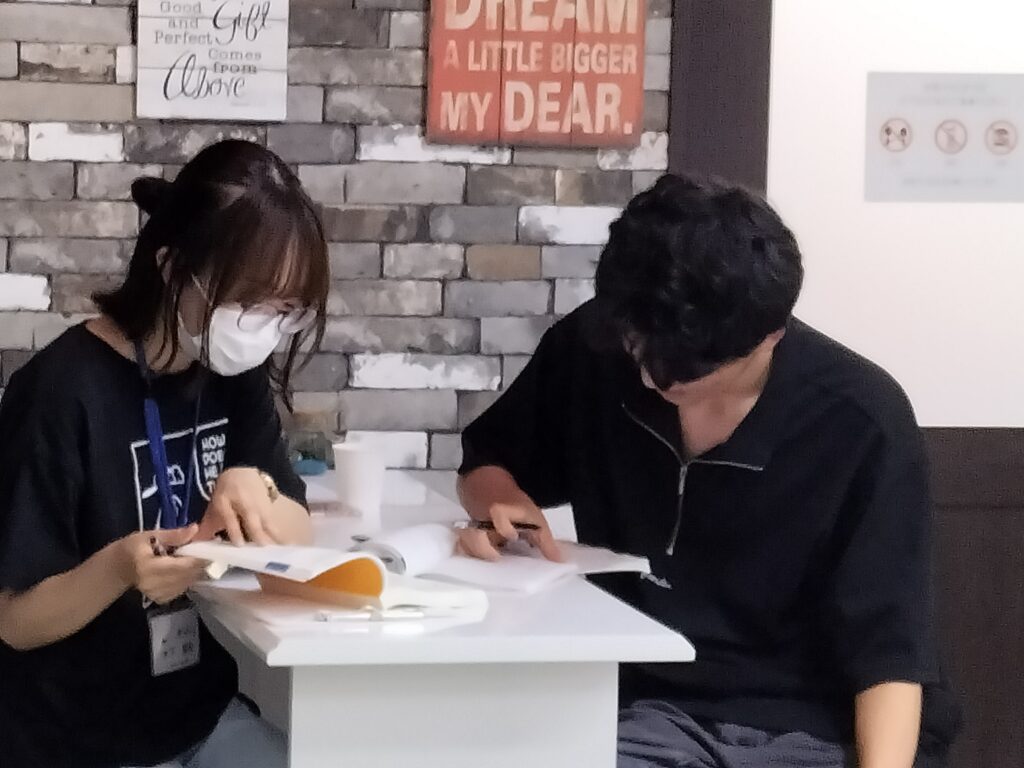こんにちは!教務副主任の三浦です。
さて、今日は経済学部に興味のある学生へのお話です。
高2の文系の学生あるいは理系で社会科学系に興味のある学生で、経済学部への進学を検討している生徒は多いかと思います。
ただ、経済学部でどんな勉強をするのかイマイチ分からないのではないでしょうか。
経済学とは何ぞやという話はそもそも経済学の定義が難しく、込み入った話になり、上手く説明できる自信がないのでやめておきます。
ということで、経済学で勉強している内容を少しでも知ってもらうために私の専攻分野の話をします。
高校生のうちに知っておくと進路の役に立つかもしれませんし、何かのきっかけになればよいということで。
私は大学で組織の経済学という分野を専攻しています。
名前から想像できるように、会社組織や官僚組織など組織の問題を経済学的に分析しようというものです。
よく分からんですね。ざっくりと解説していきましょう。
まず、ここでいう組織の問題には色々なものがあるのですが、代表的なものとして「調整の問題」というものがあります。
例えば次のような仮想的な状況を考えてみてください。
2つの事業部を抱える会社で、あるプロジェクトが実行されることになりました。
このプロジェクトは作業Aと作業Bという2つの工程からなります。
つまりプロジェクトが成功するためには、例えば事業部1が作業Aを担当して、事業部2が作業Bを担当するというように2つの事業部が別々の作業を行わなければなりません。
逆に、事業部1と2の両方が作業Aを担当してしまうように両方の事業部が片方の作業に集中してしまう場合、プロジェクトに必要な工程である作業Bが誰にも担当されないということになり、プロジェクトは失敗してしまいます。
さて、このとき事業部1と2は二つの作業を上手に分担して、プロジェクトの成功を実現できるでしょうか。
これが「調整の問題」といわれるものです。
組織の経済学ではこの問題を「経済学的」に分析します。
具体的にはゲーム理論という数学的手法を使って分析します。
ゲーム理論の説明は長くなるのでやめておきます。気になる人はWikipediaあるいは最後に紹介する文献を読んでみてください。
ところで、先ほどの「調整の問題」を解決するのは一見すると簡単なように思えますよね。
例えば、会社のより上層部が各事業部に別々の作業を割り当てればよさそうですし、あるいは事業部同士がコミュニケーションを取ることで、どちらもが同じ作業に従事するという失敗を防ぐことができそうです。
しかし、会社の社長が作業を割り当てる場合、どの事業部にどの作業を割り当てるのが最も効率的でしょうか。
会社の上層部が権限を持つことは「調整の問題」を解決する方法として有効ではありますが、一方で現場のことを一番知っているのは現場で働く人間です。
したがって、それぞれの事業部は自分たちが得意な作業ではなく、苦手な作業を担当させられるかもしれません。
また、事業部同士でコミュニケーションを行う場合でも、事業部間の利害関係が異なるために、コミュニケーションがうまくいかない可能性があります。
例えば、事業部1が「作業Aをします」というメッセージを事業部2に伝達したとします。
ここで事業部1と事業部2は異なる目的を持つ場合、事業部2はこう考えるかもしれません。
それは「事業部1は作業Aをするとは言っているものの、本当は作業Bの方がしたいのではなかろうか」といったものです。
要するに、事業部2にとって事業部1の発言が信頼できないのです。このようなとき、事業部1のメッセージはもはや何の意味も持たず、結果的に「調整」に失敗するかもしれません。
さて、随分と長くなりましたが、「調整の問題」の奥深さを少しは知ってもらえたのではないでしょうか。
繰り返しになりますが、組織の経済学ではこうした問題をゲーム理論という方法を用いて分析します。
そこで最後に、高校生でも読めるゲーム理論の入門書をいくつか紹介して終わります。興味のある方は是非手に取って読んでみてください!
鎌田雄一郎「16歳からのはじめてのゲーム理論‘‘世の中の意思決定’’を解き明かす6.5個の物語」「ゲーム理論入門の入門」
松島斉「ゲーム理論はアート 社会のしくみを思いつくための繊細な哲学」